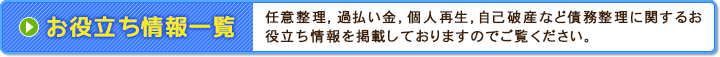「債務整理」に関するQ&A
夫(妻)の借金について、妻(夫)が返済義務を負いますか?
1 基本的には配偶者が返済義務を負うことはありません
原則として、夫婦であっても、配偶者の借金について、返済義務を負うということはありません。
金銭を借り入れる契約は、契約の当事者(貸金業者等と借入れた方)にのみ法的な効力が及びます。
借金の返済は借入れた方のみの責任であり、配偶者に法的な返済義務はないのが通常です。
例えば、夫が消費者金融からお金を借りたとしても、原則として妻には返済の義務は発生しません。
ただし、以下のケースにおいては、配偶者にも返済義務が生じることがあります。
2 配偶者が連帯保証人になっている場合
厳密には、連帯保証債務は、貸金業者等と連帯保証人との間の契約に基づくものですので、借金をしている方の配偶者の債務とは異なります。
もっとも、実際には、連帯保証人は借金をしている方の配偶者とほぼ同じ責任を負う立場になります。
法律上は、借金をしている配偶者が返済できる状態であっても、貸金業者等は連帯保証人になっている配偶者に対して支払い請求をすることができます。
特に夫婦の場合、家族だからと何となく署名してしまった結果、配偶者の借金を肩代わりせざるを得ない状況に陥るケースもあります。
3 日常家事債務である場合
実務上あまり多くは見受けられませんが、法律上は、夫婦の片方による金銭の借入れが日常家事債務に該当する場合、民法761条によって、もう片方の配偶者が連帯責任を負う可能性があります。
【参考条文】民法
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)・日常の家事に関する債務の連帯責任
日常の家事に関する債務とは、夫婦や家族が共同生活を営むうえで必要とされる日用品の購入や、娯楽、医療、教育上の債務等が含まれると考えられています。
具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるとされています。
生活をするのに必要な範囲での食品や日用品の購入のための借入れ、一般的な範囲における子の学費の借入れなどは、日常の家事に関する債務に該当する可能性があります。
無職なのですが、債務整理できますか? 債務整理をすることで失うものはありますか?